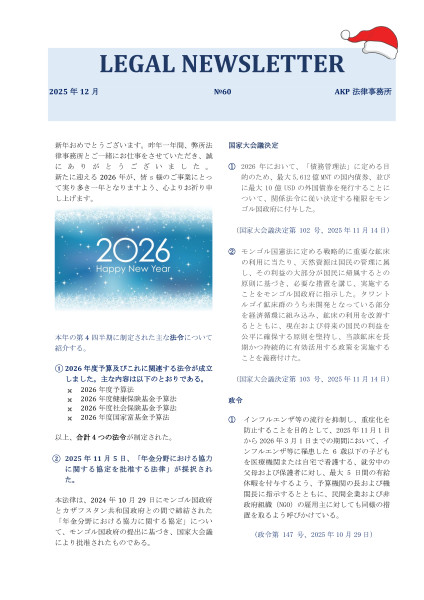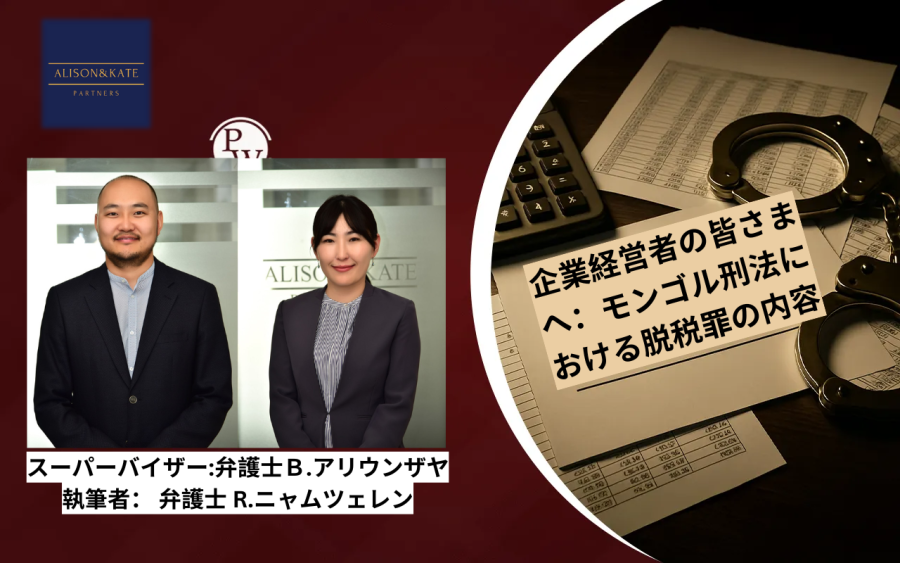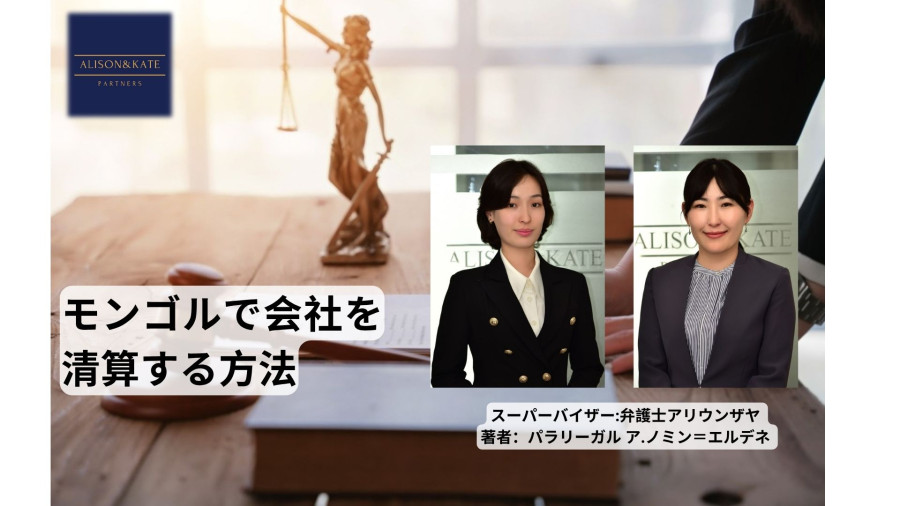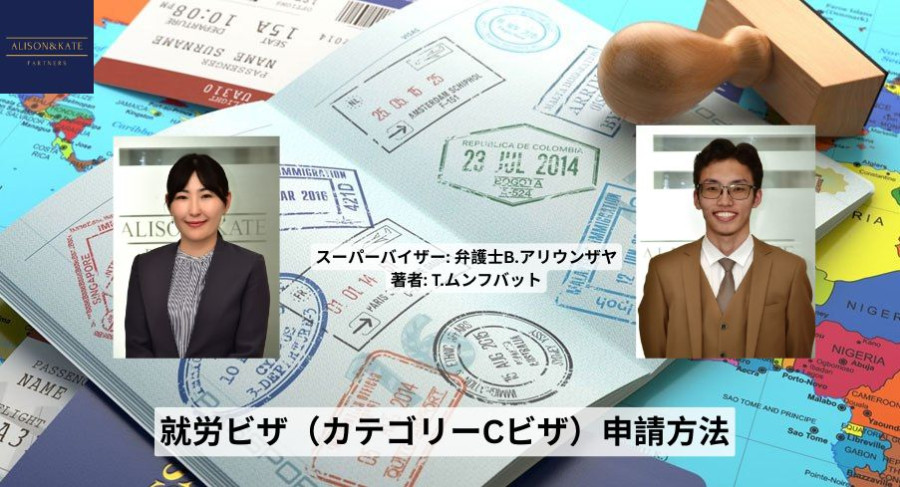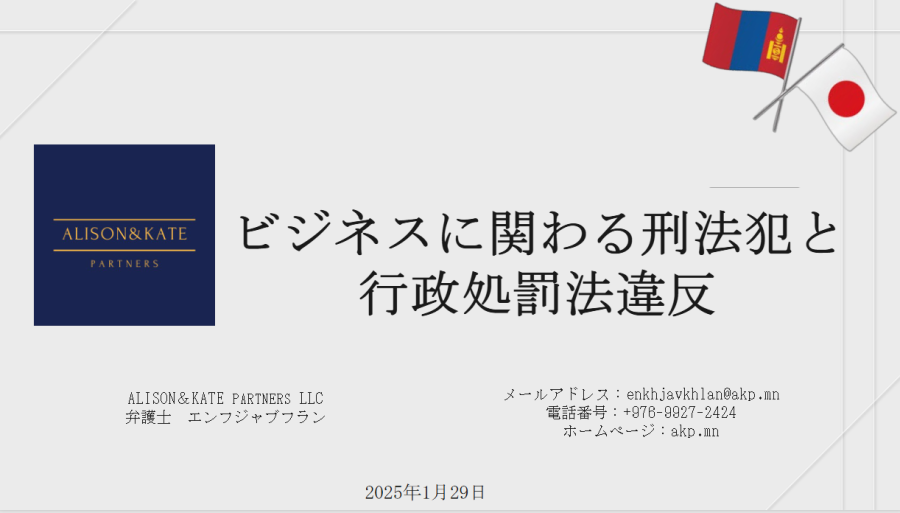法的枠組みに基づく債権回収方法
Posted by: Alison&Kate Partners
Date: 2025-09-15
Category: 記事

著者:パラリーガル T. ムンクバート
AKP法律事務所では、法的知識を専門的かつ実務的な観点からご提供することを目的として、法務ブログシリーズを発信しております。
個人間においては貸付契約に基づく元本や利息の回収が困難となる事例が多く、また企業間取引においても商品やサービスの提供後に代金を回収できない事案が頻発する場合があります。
本稿では、契約に基づく債権を回収する手段について、非司法的手段および司法的手段に分けて解説いたします。
本稿の内容は以下の通りです:
1. 非司法的債権回収
1.1. 催告書の送付
1.2. 和解契約
1.3. 調停
1.1. 催告書の送付
1.2. 和解契約
1.3. 調停
2.司法的債権回収
2.1. 民事裁判所
2.2. 仲裁
2.1. 民事裁判所
2.2. 仲裁
3.判決の執行
4.費用
5.債権回収における重要な留意点
1. 非司法的債権回収
裁判手続に進む前に、当事者間での協議や合意形成を図ることは、双方にとって費用と時間の節約につながるため、弁護士としてまず推奨する手段です。
1.1. 正式な催告書の送付
ます、債務者に対し、支払義務の不履行に伴うリスク並びに法的責任について、具体的かつ明確に通知するため、正式な催告書を送付することが求められます。催告書には、支払期限及び期限までに履行がなされない場合の法的結果を明示する必要があります。当該書面は後の裁判における証拠資料として利用可能です。
また、催告書の内容や法的責任の記載については、弁護士に相談することを強く推奨します。
1.2. 和解契約
分割払いや一部免除等の条件で債務整理について債務者と合意に至った場合には、和解契約を締結します。これにより、双方の時間及び費用を大幅に節約できる場合があります。
和解契約は公証人による公証を受けることを強く推奨します。公証済みの契約は、将来的に裁判手続きを省略できる場合があり、時間と費用の節約につながります。
和解契約は公証人による公証を受けることを強く推奨します。公証済みの契約は、将来的に裁判手続きを省略できる場合があり、時間と費用の節約につながります。
1.3. 調停
当事者間の直接交渉が不調に終わった場合には、民事・労働・家族関係に基づく紛争について調停を利用することが可能です。調停者の役割は、当事者が双方の利益にかなう解決策を見つけるのを支援し、対立や紛争を円満に、迅速かつ低コストで解決することです。
2. 司法的債権回収
和解による解決が困難な場合は、弁護士の助力を得て裁判手続により債権回収を行います。
2.1. 民事訴訟
債務者の住所地を管轄する第一審民事裁判所に訴状を提出し、裁判所による紛争解決を求めます。訴状には、契約書、サービス提供や納品を証明する書類、口頭契約を裏付ける証拠資料などを添付する必要があります。
2.2. 仲裁手続
契約において仲裁条項が設けられている場合、仲裁裁判所に申し立てを行い紛争解決を図ることが可能です。仲裁手続においても、訴状の作成や証拠の整理については弁護士の助言を得ることが望まれます。
3. 判決の執行
裁判所により判決が確定しても、債務者が任意に履行しない場合があります。この場合、債権者は裁判所に強制執行の申立てを行い、執行文書を取得したうえで、執行機関を通じて判決の強制履行を実現します。

4. 費用
当事者間で和解が成立すれば、訴訟費用や時間的負担を大幅に軽減できます。一方、訴訟に移行する場合は、弁護士費用や印紙税などが発生し、その金額は請求額に応じて異なります。具体的費用については、管轄裁判所、または弁護士に確認することが推奨されます。
5. 債権回収における重要な留意点
口頭契約及び現金・物品による取引は、裁判においてその存在及び内容を立証することが著しく困難である。よって、商品を販売する場合、サービスを提供する場合、または財産を貸与する場合には、必ず書面による契約を締結することが推奨される。
個人間の契約については、可能な限り公証人による認証を受けることが望ましい。これにより、紛争発生時に裁判で主張を裏付ける有力な証拠を確保することができる。
正式な契約書を締結できない場合、又は緊急に取引を行う必要がある場合には、以下の方法により、取引の事実を証拠として残すものとする。
商品の販売の場合:納品書又は受領書を作成し、相手方の署名・押印を得ること。 業務又はサービスの提供の場合:関連する電子メール、チャット記録、その他の取引資料を保存・保管すること。 財産や金銭の貸与の場合:現金による授受を避け、振込その他の送金方法を用いるとともに、取引目的を「貸付」「貸与資金」等と明記すること。現金による取引は、後に裁判等において証拠能力が低く、立証が困難となるためである。 いずれの場合においても、将来紛争が生じた際に取引の存在及び内容を立証し得る証拠を確実に残すことが重要である。 お問い合わせ・詳細情報
本稿に関連する詳細なアドバイスや情報については、以下までご連絡ください。
Eメール:contact@akp.mn
電話:7704-1414
本稿に関連する詳細なアドバイスや情報については、以下までご連絡ください。
Eメール:contact@akp.mn
電話:7704-1414